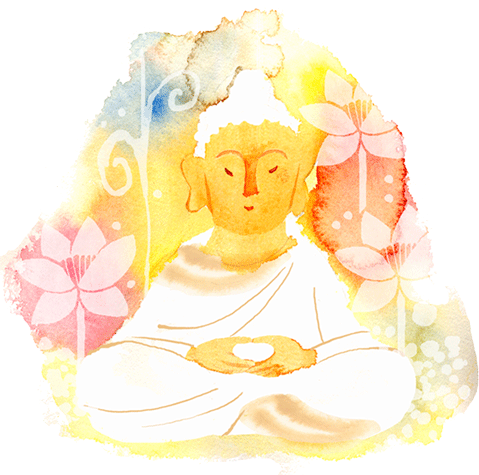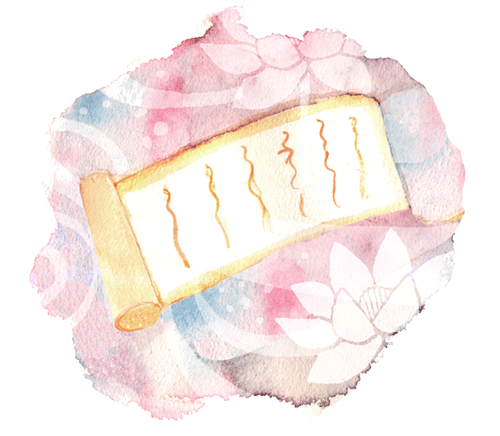第20章
●敬いの心があなたを幸せにする
常不軽菩薩品
【じょうふきょうぼさっぽん】
ヒデリノトキハナミダヲナガシ
サムサノトキハオロオロアルキ
ミンナニデクノボートヨバレ
ホメラレモセズ
クニモサレズ
サウイウモノニ
ワタシハナリタイ
詩人であり、童話作家であり、教育者であり、農業技術者であった宮澤賢治の『雨ニモマケズ』の末文であります。『雨ニモマケズ』は昭和6年(1931)11月3日、賢治の手帳に認められ、次項にはお題目が記されています。賢治は37歳という若きで早逝しますが、没後、彼の数々の作品が日の目を浴びるなかで、手帳に書き付けられていた「雨ニモマケズ」は脚光を浴びました。ここにある「デクノボートヨバレ」は、法華経第20章に説示される常不軽菩薩のことであります。
東北地方は、やませ・冷害という厳しい自然環境にしばしばさらされます。「ナミダヲナガシ」「オロオロアルキ」という表現はそれをよく表わしているといえましょう。しかし、賢治は貧しくとも農民は心豊かな生活を送るという信念を持たなければならないとし、それを推奨するために自ら農業技術者として活躍しました。人々からどんな批判があろうとも、東北の人々を敬い、人間礼拝をする。それは正に常不軽菩薩の行法そのものであったのです。
賢治が影響を受けた常不軽菩薩はどのように法華経で描かれているのでありましょうか。法華経第20章常不軽菩薩品において、お釈迦さまは得大勢菩薩(とくだいせいぼさつ)*1という方を相手として、仏さま入滅後の菩薩行の在り方、「六根清浄」の果報を得たことを実証した菩薩として常不軽菩薩の故事、行法が示されています。
昔むかし、無量阿僧祇劫の昔、大成という国に威音王如来(いおんのうにょらい)*2という仏が在りました。威音王如来が亡くなり、正法が減して像法の時代となった時、増上慢*3の四衆*4が大いに勢力を得て仏法を破壊していました。
その時に常不軽*5と名づけられる一人の修行僧があり、四衆と出会うたびに合掌礼拝して『私はあなたを敬います』、
我れ深く汝等を敬う、敢て軽慢せず、所以は何ん、汝等皆菩薩の道を行じて、当に作仏することを得べし(我深敬汝等。不敢軽慢。所以者何。汝等皆行菩薩道。当得作仏)
という二十四文字を発し、経典読誦を専らせず但だ礼拝の修行「但行礼拝(たんぎょうらいはい)」をのみを続けました。四衆の多くは、自分のことをバカにされたと思い不快感を抱き、怒り悪意を持ちののしったのです。それでもその修行僧は二十四文字を唱え続けたのでした。常にこの二十四の文字を発し常に相手を軽んじないということから、増上慢の四衆たちは、「常不軽」という綽名(あだな)を付けたのです。
このように修行僧は、法華経を読誦することなく、また、瞑想することもなく、ただ人々に合掌礼拝することを修行としていました。心清らかにただひたすらに相手を信じる、仮令、迫害を受けてもその人を信じ続ける、謂わば”人間礼拝“であります。
更に、進んでいきますと、常不軽菩薩が大変な方であることが語られるのです。常不軽菩薩はその生命を閉じようとした時、法華経の偈文を聞き六根清浄の功徳を得、その結果寿命がさらに延びて人々のために法華経を説くことになります。これを聞いた増上慢の者たちも皆信伏したと説かれます。
そして、常不軽菩薩は生命尽きた後、法華経を更に受持読誦して他者のために説き、諸仏を供養したことから仏となります。実は、その仏こそが今のお釈迦さまであると明かされるのです。お釈迦さまは、過去世において常不軽菩薩であった「則ち我が身是れなり」と、自ら告げられているのです。前世、過去世のお釈迦さまの出来事、物語のことを前生譚(ぜんしょうたん)といいます。常不軽菩薩の二十四文字の修行、つまり、誰にでも合掌礼拝し、ほめたたえた「但行礼拝」の修行は、第十六章如来寿量品で示された「我本(もと)菩薩の道を行じ」という過去世におけるお釈迦さまの菩薩行と受け取ることができるのです。
日蓮聖人にとっても、常不軽菩薩は法華経布教実践の手本的存在でありました。ご遺文には数多くの常不軽菩薩の名が登場します。日蓮聖人は「但行礼拝」の二十四文字について次のように明かしています。
かの二十四字とこの五字と、その語ことなりといえども、その意これ同じ。かの像法の末とこの末法の初と全く同じ(『顕仏未来記』文永10年(1273)5月11日 祖寿52)
二十四字とお題目の意は同じであると。二十四文字はお題目に他ならないと断言されているのです。即ち、常不軽菩薩はお題目を唱えられ、お題目の下種結縁(げしゅけちえん)の修行によって「仏身」、「仏と成った」結果を見たと解釈されたのであります。
注
*1 大勢至ともいい、極楽世界における智慧第一の菩薩で阿弥陀仏の弟子
*2 法華経を説く音声は優れ、大きな力で人々に大利益を得せしめる仏
*3 未熟であるのに自分は仏法に精通し、仏行を行っていると思っている者
*4 比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷
*5 サンスクリット訳ですと「常に軽蔑された男」となる